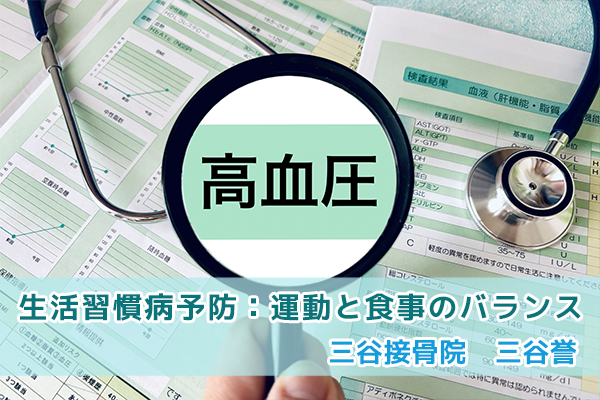
第28回:生活習慣病予防:運動と食事のバランス
「運動×食事で防ぐ生活習慣病:日々の習慣を変えて健康寿命を延ばす」
[はじめに]
皆様、今回は「生活習慣病予防:運動と食事のバランス」に焦点を当て、糖尿病、高血圧、脂質異常症などの生活習慣病の予防策について考えます。運動と食事は健康管理の基本であり、適切な習慣を取り入れることで病気のリスクを軽減できます。
① 身体の機能面
適度な運動は、血糖値のコントロール、血圧の安定化、コレステロール値の改善に効果があります。特に、有酸素運動は心肺機能の向上に寄与し、血流を促進することで代謝を改善します。
② 精神面
運動はストレスを軽減し、モチベーションを高める効果があります。食事管理がストレスになりがちな方も、適度な運動を取り入れることで、前向きな気持ちで健康習慣を続けやすくなります。
③ 具体的な運動内容
- ウォーキングやジョギング:心肺機能を向上させ、脂肪燃焼を促します。
- 筋力トレーニング:基礎代謝を上げ、体脂肪の蓄積を防ぎます。
- ストレッチやヨガ:リラクゼーション効果があり、ストレスホルモンの分泌を抑えます。
④ 福祉用具や住宅改修について
自宅で運動を行う際には、運動用マットやエクササイズバンドの活用が有効です。また、室内でも歩行しやすい環境づくり(段差の解消など)を進めることで、運動習慣を持続しやすくなります。
⑤ 病気に関する知識
生活習慣病は、遺伝的要因に加えて、長年の生活習慣の蓄積によって発症することが多い疾患です。運動と食事のバランスを意識することで、予防や症状の改善につながります。
⑥ その月のテーマと栄養について
生活習慣病予防のためには、塩分や糖分を控え、食物繊維が豊富な野菜、魚、大豆製品を積極的に摂取することが推奨されます。
[まとめ]
運動と食事のバランスを整えることが、生活習慣病予防の鍵となります。このニュースレターが、皆様の健康維持のためのサポートとなれば幸いです。
次回は「振り返り:機能訓練の成功事例と教訓」に焦点を当て、これまでの取り組みを振り返ります。
三谷接骨院 三谷誉
【出版本のご案内】
機能訓練指導員としての パーキンソン病等に対する理解 機能訓練指導員実務シリーズ Kindle版
機能訓練指導員として、私たちは利用者の身体機能を維持し、向上させるために重要な役割を担っています。特に、パーキンソン病やパーキンソン症候群、パーキンソニズムといった神経変性疾患は、利用者の運動機能や生活の質に大きな影響を与えるため、これらの疾患に対する深い理解と適切な対応が求められます。 このための知識習得と実際の機能訓練についての書籍です。
※AmazonのKindle会員様は無料でご覧になれます。






